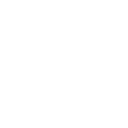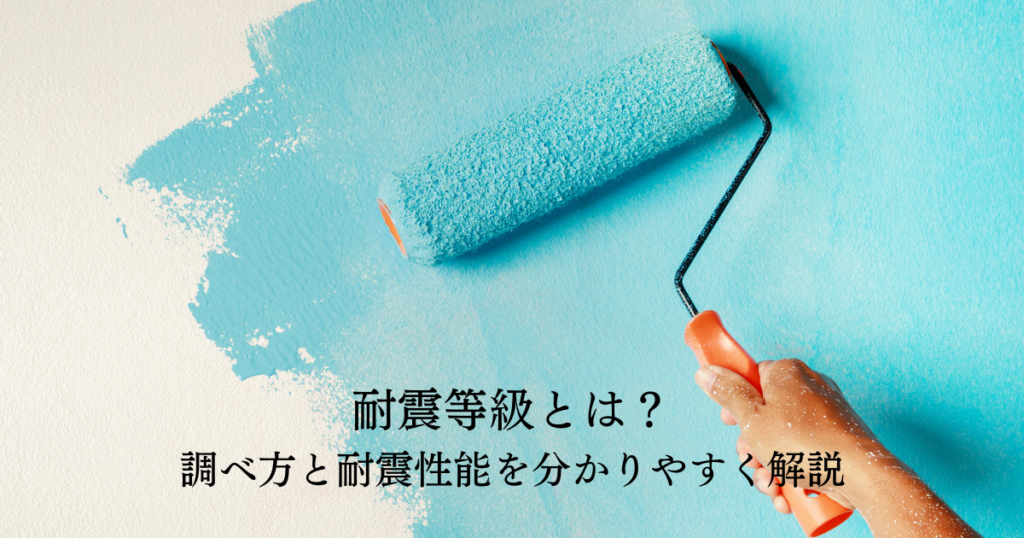地震はいつ起こるか分かりません。
しかし、日本に住む以上、地震への備えは不可欠です。
特にマイホームを購入する際には、家の耐震性についてしっかり確認しておきたいですよね。
今回は、耐震等級の調べ方について、具体的な方法を分かりやすく解説します。
耐震等級の種類や地震保険との関係についても触れ、マイホーム購入検討中の方が安心して家選びを進められるようサポートします。
耐震等級とは何かを理解する
耐震等級の定義と重要性
耐震等級とは、建物の耐震性能を表す指標です。
2000年施行の「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に基づく住宅性能表示制度で定められており、地震に対する建物の強さを数値で示します。
耐震等級が高いほど、地震に強い建物であることを意味します。
これは、建物の倒壊や損傷を防ぐために非常に重要な要素です。
耐震等級は、住宅の安全性だけでなく、地震保険の割引適用や住宅ローンの金利優遇にも影響するため、マイホーム購入を検討する際には必ず確認しておきましょう。
耐震等級1〜3の違い
耐震等級は1~3の3段階で評価され、数字が大きいほど耐震性能が高くなります。
耐震等級1は建築基準法で定められた最低基準と同等で、震度6強~7程度の地震で倒壊せず、震度5強程度の地震で大きな損傷を受けないレベルです。
耐震等級2は耐震等級1の1.25倍、耐震等級3は耐震等級1の1.5倍の耐震性能を有しています。
具体的には、耐震等級3の建物は、震度6強~7程度の地震の1.5倍の力にも耐えられる設計となっています。
2016年の熊本地震では、耐震等級3の住宅は大きな被害を受けなかったという報告もあります。
耐震等級と地震保険の関係
耐震等級が高いほど、地震保険の割引率が高くなります。
耐震等級1で10%、耐震等級2で30%、耐震等級3で50%の割引が適用されるケースが多いです。
地震保険は、地震による住宅被害に対する補償を受けるための保険です。
耐震等級が高い住宅は地震による被害が少ないため、保険料が安くなるのです。
これは、経済的なメリットとしても非常に大きいです。

耐震等級の調べ方 必要な書類と手順を解説
住宅性能評価書による確認方法
最も確実な方法は、住宅性能評価書を確認することです。
住宅性能評価書には、建物の耐震性能を含む様々な性能が記載されています。
新築住宅であれば、建築会社から交付されることが多いです。
中古住宅の場合は、売主や不動産会社に問い合わせて確認しましょう。
住宅性能評価書がない場合は、後述する方法で確認する必要があります。
第三者機関による耐震診断
住宅性能評価書がない場合、第三者機関に耐震診断を依頼することで耐震等級を調べることが可能です。
耐震診断は専門家が建物の状態を調査し、耐震性能を評価するものです。
費用は建物規模や調査内容によって異なりますが、数十万円程度かかることが多いです。
建築時期からの推定方法
住宅性能評価書や耐震診断が難しい場合は、建築時期から耐震性能を推定する方法があります。
1981年6月1日以降に建築確認を受けた建物は、新耐震基準を満たしている可能性が高く、最低でも耐震等級1相当の耐震性能を有していると推測できます。
しかし、これはあくまで推定であり、正確な耐震性能を知るには専門家による診断が必要です。
耐震等級が記載されている可能性のある書類
耐震等級は、住宅性能評価書以外にも、建築確認申請書や設計図書などに記載されている可能性があります。
これらの書類は、建築会社や不動産会社に問い合わせることで入手できる場合があります。
まとめ
今回は、耐震等級の調べ方について、住宅性能評価書による確認、耐震診断、建築時期からの推定、その他の書類からの確認など、複数の方法をご紹介しました。
耐震等級は、地震に強い家を選ぶ上で重要な指標です。
マイホーム購入を検討する際には、必ず耐震等級を確認し、ご自身の予算や希望する安全レベルと照らし合わせて最適な選択をしてください。
地震保険の割引適用についても考慮し、総合的に判断することが大切です。
耐震等級以外にも、地盤の強度や建物の構造なども考慮に入れ、安心安全な住まいづくりを進めていきましょう。
地震への備えは、大切な家族を守ることに繋がります。